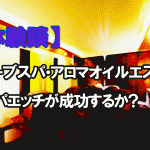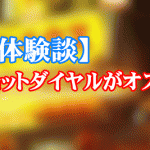小宮れいなさん(26歳・女性・東北在住・地方都市の専業主婦)
地方在住の専業主婦・小宮れいなさんから届いたのは、テレビ電話アプリを通じて心と身体が解放されていく一夜の記録です。
もともとは寂しさ紛れに始めたアプリの利用。
しかし画面越しの“声”に心が揺れ、相手の男性・涼真さんとの距離はLINEをきっかけに急速に縮まっていきます。
最初は軽い雑談だった関係が、気づけば下着姿を見せ合い、指先で自分を慰め合うほどに……
「もう、引き返せないかもしれない」――そう感じながらも、人妻のれいなさんはその快感に溺れていきました。
結婚3年目、夫とはすっかりセックスレス。
夜の生活に満たされないまま、ただ「妻」として日々を過ごすうちに、
心も身体もどこかで刺激を欲するようになっていった。
ある夜、偶然インストールしたアダルト向けテレビ電話アプリ。
最初はただ誰かと話したかっただけのはずが、
スマホの向こうで視線を絡ませ、言葉で身体を煽られ、
気がつけばパンティの中はぐっしょり濡れていた――
この体験談は、そんな“人妻の秘められた夜の吐息”を綴ったリアル告白です。

今回の記事におすすめエロビデオ通話アプリ・サイト
見知らぬ声に欲情していく人妻
結婚して3年目。
夫の帰りは遅く、私との夜の営みもすっかりご無沙汰になっていた。
日常の中で満たされない気持ちを抱えていた頃、スマホにふと表示されたのが「VI-VO」というテレビ電話アプリ。
通話越しに誰かと話すだけでもいいかな、そんな軽い気持ちで覗いてみた世界が、まさかここまで私の欲望を暴き出すなんて思いもしなかった。
最初はただ軽く雑談していただけだった。
通話相手の男性は、「涼真」と名乗った。
声が低くて落ち着いていて、なのにその奥に妙な艶があった。
言葉は優しいのに、どこかじっと見透かすような気配がある。
彼は私のプロフィールを見て、笑いながらこう言った。
「人妻なんだね。なんだか……声が寂しそうだよ」
図星だった。
知らない男のその言葉に、胸の奥がずきっと疼いた。
「今どんな格好してるの?」
ふいにそう訊かれた。
そのとき私は、夫がいない夜の寂しさを少しでも埋めるように、
レースの透けたベビードールをパジャマの下に着ていた。
誰に見せるわけでもないのに、なんとなく下着だけは可愛いものを選んでいた自分を思い出し、恥ずかしくなる。
「もこもこのパジャマ着てるよ」
そう答えると、涼真さんの声が少し低くなった。
「それ……脱いでみて。俺の前だけ、ちょっとだけでいいから」
画面越しにそんなことを頼まれるなんて、想像もしなかった。
でも、カメラの前の私は、なぜかすぐにパジャマのボタンに手をかけていた。
カメラ越しに晒す、人妻の裸欲
パジャマをそっと脱ぎ、肩から滑り落ちるレース地の布が肌に触れて、なんとも言えないゾクゾクした感覚が走る。
カメラの前にベビードール姿を見せた瞬間、涼真さんが深く息を吸い込む音がマイク越しに聞こえた。
「うわ…エロい…。人妻がこんな格好して、誰に見せるつもりだったの?」
言葉が鋭く突き刺さる。
私はただ俯いて、「…見せるつもりなんてなかったよ」と呟いた。
「でも……今は俺に見せてるよね?」
その一言で、全身がビリビリと熱くなった。
まるで、夫にも見せたことのない何かを、知らない男に見透かされているようだった。
涼真さんの指示はさらに続いた。
「ちょっとだけ、指舐めてみて」
正直、ためらいはあった。
けれどカメラ越しの男の目に欲を感じて、どこか支配されるような快感が混ざっていた。
私は人差し指と中指を揃えて、そっと唇に差し入れる。
ぬるりとした感触と共に、舌が指に絡みつく。
「……れいな、俺の名前呼んで。呼びながら、その指をもっとねっとり舐めて」
れいな、と下の名前を呼ばれたのは久しぶりだった。
その響きに、何かが壊れていく。
「涼真…ん…しりたいの…もっと…見てほしい…」
自分でも驚くほど甘い声が口をついて出る。
知らない男の名前を呼びながら、舐める音が通話越しに響き、
涼真さんのマイクからも荒い吐息が漏れてくる。
その瞬間、ビデオ通話のカメラにふっと指がかかり、彼がズボンの中で自分を扱いている様子がチラリと見えた。
息をのむ私に、彼が囁く。
「……もっと見せてよ。その下、脱いでいい?」
心はもう、ほとんど濡れていた。
だけど私は、ギリギリのところで踏みとどまり、首を横に振った。
「今日はここまで…じゃないと、ほんとに止まれなくなるから」
「…じゃあ、次は覚悟してて。俺、もっと……乱したい」
その言葉に、次の夜が待ち遠しくなってしまった私は、
もうすっかり、この快楽の中に足を踏み入れてしまっていた。
LINE越しの距離が、もっと近く感じた夜
あの夜のやりとりをきっかけに、涼真さんとはLINEを交換するようになった。
はじめは軽い雑談だった。
「今日もお疲れさま」とか、「夕飯なに作った?」とか、まるで普通の知り合いのような関係。
でも、ほんの数回のやり取りだけで、私は既に彼を“ただの男”として見ていなかった。
年齢は私より10歳ほど上。営業の仕事で日々いろんな女性と話しているらしい。
落ち着いた雰囲気と、言葉の端々に感じる余裕…。
夫にはない「私を見つめてくれている感覚」に、心の奥がじんわりと溶けていった。
「ねぇ、今夜…旦那さん、家にいないんだっけ?」
その一言が届いたのは、夫が数日出張で不在の夜。
私は「うん」とだけ返信を返すと、すぐに通知音が鳴った。
──LINE通話、着信中。
画面に浮かぶ“涼真”の名前をタップしたとき、すでに私はパジャマの下に何を着ているかを意識していた。
スマホの画面越しに囁かれた命令
「久しぶりに顔見れて嬉しいな。なんか色っぽくなった?」
画面越しの涼真さんは、相変わらず落ち着いた表情をしていた。
けれどその目は、どこかじっと私を射抜くようで、呼吸が浅くなる。
「今日は下、どんな下着つけてるの?」
そんな質問をさらりと聞ける男って、ずるいと思う。
「白の…レースの、ちょっと透けるやつ」
「……見せてくれる?」
私はスマホを枕元に立てかけて、ゆっくりとパジャマのズボンを腰まで下ろした。
レースの布越しに浮かぶ自分のアソコに、少し羞恥が込み上げる。
けれど、そのすぐ先に涼真さんの視線があると思うと、息が詰まるほど興奮した。
「ブラも、取ってみようか」
私の手が震えながら背中のホックを外し、画面の隅に胸を映した瞬間――
「うん…綺麗。もっと見せて。胸の先、指でなぞってみて」
命令のような囁きに従って、私はゆっくりと乳首を指でなぞる。
すでに先端は固くなっていて、軽く触れるだけでゾワリと痺れる。
そのとき、彼のカメラがスッと下に向けられた。
ズボンの奥から現れた彼の性器に、私の喉が無意識に鳴った。
「どう? 触りたくなった?」
返事はできなかった。
でも、手はいつの間にか自分の脚の間へと伸びていた。
画面越しに絶頂へ導かれた人妻
「ちょっとだけ、舐める仕草してみて」
涼真さんの声に応えるように、私は手元にあったボールペンをそっと咥え、
ゆっくりと上下に動かした。
唇の動きと、舌先が絡むその仕草が、スマホのマイク越しにくっきりと音になって響いた。
「えっちだな…。次は、自分の指で奥を撫でて。声も出して」
私の指がショーツの中に滑り込むと、すでに熱を持った秘部がぬるりと濡れていた。
息が漏れる。
恥ずかしいはずなのに、声が勝手にこぼれてしまう。
「涼真…見て…私、変になっちゃう…」
「いいよ、もっと声聞かせて」
彼の動きも徐々に早くなり、お互いの荒い息遣いがスマホの中で交錯する。
まるで触れられているような錯覚すら覚えるほど、音と視線が絡みついて離れない。
やがて、彼の低い吐息が喉奥で震えたと思った瞬間――
「…イキそう…れいな…っ!」
その声に背中が震え、私も一気に指の動きを早めて、全身が熱に包まれたまま絶頂を迎えた。
しばらく2人とも言葉を失ったまま、ただ画面を見つめていた。
「……れいな、やっぱり可愛いよ。人妻って感じ、最高」
私は少し笑って、「それ褒めてるの?」と返した。
けれどその言葉に、また体が火照り始めているのを自分でも感じていた。
管理人からひと言
れいなさんの体験談を通じて感じたのは、“声”と“視線”が織りなす濃密なエロスの力でした。
夫との性生活が薄れ、誰かに見られたい、感じてほしいという欲求が静かに高まっていた日々。
そんな彼女にとって、涼真さんとの出会いはまさに導火線に火をつける瞬間だったのだと思います。
画面越しの指示に従いながら、徐々に露わになっていく肌、呼吸の熱、舌の動き――
全てが「妻」ではなく「ひとりの女」としての自分を呼び起こす体験だったはずです。
ビデオ通話という限定的な空間だからこそ生まれるスリルと安心感。
それは罪悪感と快感が入り混じる、背徳のオアシスなのかもしれません。
れいなさんのように、誰にも言えない欲望を秘めた人妻たちは、今日も画面の向こうで誰かを待っているのかもしれませんね。